お知らせ & コラム NEWS / COLUMN
倦怠感〜「何となく疲れが取れない」あなたへ〜
朝起きても体が重い、休日にゆっくり休んでも疲れが抜けない──そんな日々が続いていませんか?
「ただの疲れかな」と思っているうちに、やる気が出ない、集中できない、ちょっとしたことでイライラする……。気づけば心身ともに不調が当たり前になっている、そんな方が近年とても増えています。
この「慢性的な倦怠感」は、単なる疲労とは違い、体と心が休息や睡眠だけでは回復できない状態にあることを示しているサインかもしれません。原因が分からないまま放置してしまうと、日常生活に支障をきたしたり、うつ病や自律神経失調症などにつながるケースもあります。
本コラムでは、「慢性的な倦怠感」という症状に焦点を当て、考えられる背景や東洋医学の視点からの解釈、そして鍼灸によるアプローチについてお話しします。
ご自身や大切な人の「なんとなく疲れている毎日」の理解と回復の一助になれば幸いです。

第1章 慢性的な倦怠感に隠れているかもしれない病態とは?
「疲れているだけだと思っていたのに、実は病気のサインだった」──このようなケースは決して珍しくありません。慢性的な倦怠感は、以下のような身体的・精神的な病態の一症状として現れることがあります。
身体的要因として考えられるもの
甲状腺機能低下症:新陳代謝が落ち、全身がだるくなります。
慢性疲労症候群(ME/CFS):明確な原因がわからないまま強い疲労が続く疾患。
自律神経の乱れ:交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、倦怠感・不眠・動悸などが出現します。
精神的要因として考えられるもの
うつ病・軽度の抑うつ状態:心の疲れが体の重さとして表れることがよくあります。
燃え尽き症候群(バーンアウト):過度のストレスや責任感の強さから来る心身の疲労。
過度のストレス:仕事や家庭、人間関係による慢性的なストレスは、体にも強い影響を及ぼします。
このように、慢性的な倦怠感は単独の症状ではなく、体や心の深層からの「助けを求めるサイン」であることが多いのです。
だからこそ、単に「疲れているから」と軽視せず、少し立ち止まって自分の状態を見つめ直すことが重要です。
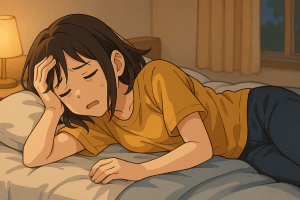
第2章 倦怠感が日常生活に与える影響とは?
慢性的な倦怠感は、ただ「体がだるい」という一言では片づけられないほど、私たちの生活のあらゆる場面に静かに、しかし確実に影響を及ぼします。
仕事や学業への支障
集中力や判断力が低下し、業務のミスが増えたり、思考のスピードが落ちて仕事が遅れたりします。
「やる気が出ない」「出勤するのが億劫」など、精神的なブレーキもかかるようになります。
プライベートな時間の質の低下
趣味や遊びに興味が湧かなくなり、休日も家で寝ているだけ。大切な家族や友人との時間を楽しむ余裕がなくなり、「楽しいはずの時間」が負担に感じられることも。
自己評価の低下
「自分はダメだ」「頑張れていない」と感じやすくなり、自信を失ってしまうこともあります。このような負の感情が、精神面にも影を落とすようになります。

慢性的な倦怠感は、身体だけでなく「心のゆとり」や「自分らしさ」までも少しずつ蝕んでいきます。そのことに気づいたときには、すでに大きなストレスや不調に発展していることも。
だからこそ、日常の小さな変化に気づくことが、症状改善の第一歩なのです。
第3章 東洋医学からみた「慢性的な倦怠感」
西洋医学では血液検査や画像検査で明らかな異常が見つからない限り、原因不明とされがちな「慢性的な倦怠感」。しかし東洋医学では、このような“なんとなく不調”にも明確な解釈とアプローチがあります。
気・血・水のバランスの乱れ
東洋医学では、人の体を「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」という3つの要素の調和によって成り立つと考えます。このバランスが崩れると、倦怠感や無気力感があらわれやすくなります。
1. 気虚(ききょ)──エネルギー不足
「気」は体を動かすエネルギー源。慢性的な疲労感、息切れ、食後の眠気などがある場合は「気」が不足している可能性があります。特に、過労やストレス、睡眠不足が続くと気が消耗し、だるさが抜けにくくなります。
2. 血虚(けっきょ)──栄養のめぐりの不足
「血」は体を潤し、心や筋肉を養う役割を持ちます。血虚の状態になると、貧血症状やふらつき、思考力の低下などが起こり、疲れが取れにくくなります。
3. 水滞(すいたい)──体内の水分循環の停滞
「水」の代謝が悪くなると、体が重く感じたり、むくみや頭のもやもや感につながります。雨の日に調子が悪くなる人はこのタイプかもしれません。

五臓との関係性
東洋医学では「五臓(肝・心・脾・肺・腎)」も倦怠感と深く関わっています。特に「脾(ひ)」は飲食物を消化吸収し、「気」を生み出す重要な臓器とされ、脾が弱ることで「気虚」にもつながると考えられています。
慢性的な倦怠感は、東洋医学の視点では“体内のバランスの乱れ”が原因とされ、個々の体質や生活習慣に応じた調整が大切だと考えられます。
表面的な症状だけでなく、体の内側から整えていく──それが、東洋医学の強みなのです。

第4章 当院の鍼灸施術──“気”の巡りを整え、根本から回復へ
慢性的な倦怠感に対して、当院では東洋医学の理論に基づいたオーダーメイドの鍼灸施術を行っています。症状の背後にある「気・血・水」の乱れや「五臓」のバランスに着目し、体全体の調和を整えることで、根本的な改善を目指します。
1. 体質や不調のパターンを丁寧に見極める
初回のカウンセリングでは、患者さんの脈・腹部・顔色・問診などから、現在の体の状態や不調の背景を詳しく分析します。例えば、「朝から重だるくて起き上がれない」「夕方になると疲れがどっと出る」など、時間帯や状況によって異なる倦怠感も体質の手がかりになります。
2. 気虚・血虚・水滞それぞれに合わせた施術
気虚タイプには、脾や肺を補う経穴(ツボ)に鍼やお灸を施し、エネルギーを補い、活力を高めていきます。
血虚タイプには、血を生み出す肝や脾を整える施術を行い、栄養と潤いを巡らせるよう働きかけます。
水滞タイプには、余分な水分の排出を促し、むくみや頭の重だるさを改善するようアプローチします。
3. 自律神経や内臓機能の調整も重視
倦怠感の多くには、自律神経のアンバランスや内臓機能の低下も関わっています。当院では、リラックスと活性を調和させる経絡やツボに鍼通電(パルス)を加えるなど、より深いレベルでの調整を行います。

鍼灸は“今出ている症状”だけでなく、“その人が本来持つ回復力”に働きかけます。
慢性的な倦怠感に悩まれている方こそ、自分の体の声に耳を傾け、根本から整えていくケアが必要です。
第5章 おわりに──「なんとなく疲れている毎日」から抜け出すために
「病気ではないけれど、ずっと体が重い」「何をしても疲れが取れない」──
そんな慢性的な倦怠感は、多くの人にとって日常の背景に溶け込んでしまっている“見えにくい不調”です。
ですが、体が発するその「だるさ」や「しんどさ」には、確かな理由があります。
無理に気合いや根性で乗り切ろうとせず、まずはそのサインに耳を傾け、自分の体に優しく目を向けてみてください。
東洋医学では、心と体を一体ととらえ、バランスを整えることで不調の根を断つことを目指します。
当院では、患者さん一人ひとりの体質や生活背景に寄り添いながら、症状の奥にある原因を見極め、丁寧にケアしていきます。
「なんとなくずっと疲れている」その状態を、「本来の元気な自分」に戻る第一歩に変えてみませんか?

お問い合わせはこちら
お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。
【グループ院のご紹介】
東京α鍼灸院:中目黒駅
三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅
吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅
高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅
Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 14:25 / 院長コラム
最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN
- 2026.01.10
- 渋谷で食いしばりにお悩みの方へ/渋谷a鍼灸院の食いしばりに対する治療
- 2025.12.24
- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術
- 2025.12.18
- 多汗症
- 2025.12.05
- 頭痛の鍼灸治療
- 2025.11.27
- 突発性難聴
- 2025.11.06
- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療
- 2025.10.28
- パニック障害の鍼灸治療
- 2025.10.12
- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療
- 2025.10.11
- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について
- 2025.09.30
- 振戦の鍼灸施術
- 2025.09.24
- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について
- 2025.09.08
- 自律神経について徹底解説
- 2025.08.27
- 東洋医学から診るパーキンソン病
- 2025.08.23
- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療
- 2025.08.14
- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療
- 2025.08.04
- 耳管開放症の鍼灸治療
- 2025.07.22
- 後鼻漏でお悩みの方へ
- 2025.07.22
- メニエール病の鍼灸治療
- 2025.07.19
- 顎関節症の鍼灸治療
- 2025.07.14
- 突発性難聴について
ご予約はこちらから
\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/
はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。
たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で
お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。
是非一度お気軽にご相談ください。

