お知らせ & コラム NEWS / COLUMN
振戦の鍼灸施術
振戦とは?
「手が震えて字が書きにくい」
「コップを持つと中身がこぼれてしまう」
「人前で震えが出てしまい恥ずかしい」
──振戦(しんせん)は、このように日常の小さな動作に影響を与える症状です。
一時的な震えは誰にでもあります。寒さや強い緊張、疲労で手が震えることは自然な反応で、休めばおさまることが多いでしょう。
ところが、明らかな理由がなく長く続いたり、生活に支障をきたすほど強くなった場合、それは「病的な振戦」である可能性があります。
振戦は加齢に伴って増えることもあり、「年のせいだから仕方ない」と見過ごされがちです。
しかし、神経や内科的な病気のサインである場合もあります。大切なのは「震えをただの老化現象と決めつけないこと」です。
そして何より知っていただきたいのは、振戦は「コントロールできない運命」ではなく、工夫や治療によって和らげる方法があるということです。症状を正しく理解することが、安心と改善への第一歩となります。
振戦の種類
振戦にはいくつかのタイプがあり、どのような場面で出るのかによって分類されます。これを知ることで、自分の震えの特徴を理解しやすくなります。
① 安静時振戦
体を動かしていない時に現れる震えです。特にパーキンソン病に多く見られ、手を膝の上に置いた時などに小刻みに震えます。
② 動作時振戦(本態性振戦)
コップを持つ、字を書くなどの動作で強まるタイプです。最も頻度が高く、遺伝的な要素も関わります。「人前で字を書くのがつらい」「食事のときに箸が使いにくい」といった悩みにつながります。
③ 姿勢時振戦
手を前に伸ばすなど、同じ姿勢を保つ時に出やすい震えです。緊張や不安で強まることが多く、精神的な影響を受けやすいのが特徴です。
④ 小脳性振戦
目標物に手を伸ばそうとすると震えが強くなるタイプです。動作の正確さに影響し、「コップに水を注げない」「ボタンが留めにくい」といった実生活の支障につながります。
このように振戦の種類によって背景は異なりますが、共通して言えるのは「適切に診断し、対応すれば生活を取り戻す道がある」ということです。
自分の震えの特徴を理解することは、不安を減らし、治療やセルフケアを前向きに考える大切な一歩です。
振戦と日常生活への影響
振戦は命に関わる病気ではありませんが、生活のあらゆる場面に支障をきたすため、ご本人にとっては大きな悩みになります。
例えば、
◯文字を書こうとすると手が震えて文字が乱れてしまう
◯コップに水を注ごうとしてもこぼしてしまう
◯ボタンを留めるのに時間がかかる
こうした細やかな作業の一つひとつが負担になり、次第に自信を失ってしまう方も少なくありません。
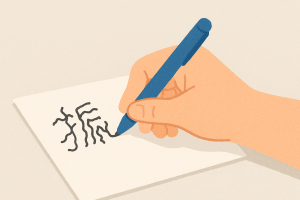
また、人前で手の震えが目立つと「周囲にどう思われるだろう」と不安になり、外出や人との交流を避けてしまうこともあります。
これが続くと、振戦そのもの以上に、孤独感や気持ちの落ち込みが強まってしまうのです。
しかし、ここで大切なのは「振戦=何もできない」ではないということです。
食器の形を工夫したり、ペンに補助具をつけたりするだけでも日常生活はぐっと楽になります。
さらに鍼灸をはじめとしたケアを組み合わせれば、震えが和らぎ「外に出てみようかな」と前向きな気持ちを取り戻せるケースも少なくありません。
つまり、振戦は確かに生活に影響を与える症状ですが、適切な治療で、その影響を小さくし、自分らしい日常を取り戻していくことができるのです。
西洋医学における治療法
振戦に対しては、まず西洋医学的な治療が行われます。代表的なのは薬物療法で、β遮断薬や抗てんかん薬などが震えを抑えるために用いられます。
これらの薬は有効なケースも多い一方で、効果の持続が限られていたり、だるさ・低血圧といった副作用が出ることもあります。
また、症状が重度で薬が効きにくい場合には、外科的治療として「脳深部刺激療法(DBS)」が行われることもあります。これは脳内に電極を埋め込み、異常な神経活動を抑える方法です。ただし侵襲的な治療であるため、誰にでも適応できるわけではありません。
つまり、西洋医学の治療には効果が期待できる一方で、限界やリスクもあるため、患者さんそれぞれに合わせた治療の選択が大切になります。
鍼灸に期待できる効果
東洋医学において振戦は、「肝風内動」「気血不足」「腎精虚」などの弁証で捉えられることが多く、自律神経系の乱れや筋肉の過剰な緊張と関連しています。鍼灸治療は全身のバランスを整え、神経・筋肉の機能を調整することで震えの軽減を目指します。
筋緊張の緩和
手指や前腕の震えには、局所の筋緊張を和らげることが重要です。合谷(LI4)・曲池(LI11)・外関(TE5)などの経穴に鍼を行い、必要に応じて低頻度の鍼通電(2〜4Hz)を加えることで、末梢筋の収縮を抑制します。

自律神経の安定化
精神的緊張や不安が振戦を悪化させることがあります。そのため百会(GV20)や内関(PC6)を用い、副交感神経を優位にしリラックス効果を高めます。特に耳周囲や頭部のツボは、不眠や精神的不安を伴うケースに有効です。
全身調整と体質改善
脾腎の弱りや気血不足が背景にある場合、足三里(ST36)、三陰交(SP6)、腎兪(BL23)などを用いて全身の気血を補い、体質改善を図ります。これにより震えの再発予防、慢性的な疲労や倦怠感の改善にもつながります。

期待できる臨床効果
☑️字を書く、箸を持つなどの細かい動作がスムーズになる
☑️緊張場面での震えが和らぎ、外出や人前での不安が軽減される
☑️睡眠の質が改善し、日中の震えが落ち着く
☑️西洋医学的治療(薬物療法)との併用により、薬の使用量を減らせる可能性がある
鍼灸は大きな副作用が少なく、継続的に取り入れやすい治療法です。患者一人ひとりの体質や症状に合わせて配穴や刺激法を工夫することで、振戦のコントロールに大きな助けとなります。

まとめ
振戦は命に直接かかわるものではありませんが、日常の細かな動作や人前でのふるまいに大きな影響を与えるため、ご本人にとっては深刻な悩みとなります。
「字が書けない」「食事がしにくい」「周囲の目が気になる」といった日常の困難は、時に心の負担へとつながります。
しかし、振戦は決して“コントロールできない症状”ではありません。薬物療法や生活の工夫、そして鍼灸をはじめとした東洋医学的アプローチを組み合わせることで、震えの程度を和らげ、安心して生活を送れるようになる可能性があります。
鍼灸は副作用が少なく、心身全体のバランスを整えながら症状にアプローチできる点が特徴です。
少しずつでも震えが落ち着き、「字が書けるようになった」「外に出るのが怖くなくなった」といった変化を実感される方もいます。
大切なのは「一人で我慢しないこと」。振戦に悩む方は、適切なサポートを受けながら自分に合った方法を見つけることで、日常生活の質を取り戻すことができます。希望を持って、一歩ずつ改善への道を歩んでいきましょう。

お問い合わせはこちら
お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。
【グループ院のご紹介】
東京α鍼灸院:中目黒駅
三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅
吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅
高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅
Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 17:16 / 院長コラム
最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN
- 2026.02.19
- 渋谷で花粉症にお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院の花粉症に対する鍼灸施術
- 2026.02.09
- 渋谷で双極性障害にお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院の双極性障害に対する鍼灸施術
- 2026.01.31
- 渋谷でパニック症にお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のパニック症に対する鍼灸施術
- 2026.01.26
- 渋谷で冬季うつにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院の冬季うつに対する鍼灸施術
- 2026.01.25
- 渋谷で自律神経失調症にお悩みの方へ/渋谷α鍼灸院の自律神経失調症に対する鍼灸治療
- 2026.01.10
- 渋谷で食いしばりにお悩みの方へ/渋谷a鍼灸院の食いしばりに対する治療
- 2025.12.24
- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術
- 2025.12.18
- 多汗症
- 2025.12.05
- 頭痛の鍼灸治療
- 2025.11.27
- 突発性難聴
- 2025.11.06
- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療
- 2025.10.28
- パニック障害の鍼灸治療
- 2025.10.12
- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療
- 2025.10.11
- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について
- 2025.09.30
- 振戦の鍼灸施術
- 2025.09.24
- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について
- 2025.09.08
- 自律神経について徹底解説
- 2025.08.27
- 東洋医学から診るパーキンソン病
- 2025.08.23
- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療
- 2025.08.14
- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療
ご予約はこちらから
\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/
はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。
たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で
お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。
是非一度お気軽にご相談ください。

